・イギリスのインド支配の目的
そもそも、イギリスは、インド人を「利用」しようとしただけで、ナチスやポル・ポト政権のように、「絶滅」させようとする意図はなかったはず。
もちろん、その「利用」の仕方は過酷で、ときには、インド人は奴隷のように働かされたらしいけど。
イギリスがインドを支配したのは、ガンディーによれば「商売」のためであり、「イギリス人たちの最高神はお金」であったという。
イギリス人たちがその国を支配するのは、商売のためと知らなければなりません。イギリス人たちの軍隊と艦隊はただ商売を守るためにあるのです
(真の独立への道 岩波文庫)

確かに、イギリスのインド支配もイギリスの軍隊も、インド人を殺傷することを目的としていたわけではない。
一番の目的は、商売であり金儲けのため。
イギリスのビジネスがうまくいくように、インドを近代化した。
インド亜大陸全土に張り巡らすような形で進められた鉄道網の整備は、いわば巨大な『公共事業投資』として行われ、イギリスの金属産業、機械産業を潤(うるお)した
(インド植民地官僚 本田穀彦)
また、イギリスがインドやインド人を利用したのは商売のためだけではない。
第一次世界大戦中にイギリス本国政府は、植民地インドに対して、100万人を超える兵員と1億4600万ポンドの資金の提供を求めた
(インド植民地官僚 本田穀彦)
このように、イギリスは戦争時に、インドにお金と兵士をも求めている。
「利用している」ということは、イギリスはインド人に必要性や価値を認めているということでもある。
ナチスやポル・ポト政権の人間は、ユダヤ人や敵対者にはそうしたことを一切認めず、ただ「害悪」であると考えていた。
ナチスは「働けるユダヤ人には、死ぬまで働かせる」という意味で、価値を見いだしていたかもしれないけど。

・インド人を「教育」したイギリス
また、イギリスは、イギリスのインド支配に役立つインド人を育てようと、教育も行っている。
イギリスは知識階級であるブラーフミンに英語をはじめ新時代に相応しい教育を授け、かれらの有能な助手に仕立てようとした
(アンベードカルの生涯 光文社新書)
当時、植民地のインドを統治するためには、優秀な役人が必要だった。
なかでもインド高等文官というポストは、限られたエリートだけがなれるもので、それは、とても魅力的な地位だった。
元インド高等文官のイギリス人は、イギリスのテレビ局でこのように話している。
人々は我々のことを『天上に生まれた者たちheaven-borns』と呼び、また、我々の側でも、その大半が、自分たちがそのように呼ばれるのにふさわしい存在なのだ、と考えていた
(インド植民地官僚 本田穀彦)
1892年のインド高等文官の採用試験の結果は、オックスフォードやケンブリッジ大学という名門大学の学生らにまじって「合格者全体の中でインド人たちが占めた割合は五・四パーセント(同書)」というものだった。
この合格率は決して高くはないかもしれないけど、イギリスはインド人にもイギリス人と同様の地位を与えていることは分かる。
「イギリス人たちは私たちの国にとって死神そのものです」と、ガンディーの本の中にあたが、ナチスやポル・ポトのような「本当の死神」ではない。
イギリスはこのように、インド人をイギリス人と(部分的かもしれないけど)同じように扱ったり、後で触れるように不可蝕民に教育の機会を与えようとしたりしている。
もちろん多少の「善」があったとしても、現在からみれば植民地支配は否定されるべきものだけど。

・ナチスとは違うイギリスのインド支配
数冊の本を読んだだけの知識だが、「同じ支配」といっても、イギリスのインド支配とナチスやポル・ポトの支配とは目的もやり方もまったく違う。
イギリス人は「お金が最高神」で、「商売」のためにインド人を「利用」していた。
ナチスやポルポト政権は、ユダヤ人や敵対者を「絶滅」させるために、アウシュヴィッツの収容所やツールスレン刑務所などをつくって、「虐殺」していた。
これら三者を同じ「支配」として、「ガンディーのやり方がナチスやポル・ポトに通じるか?」というあのおじさんの質問自体に無理があるような気がする。
あのおっさんめ!

・インド人を「家畜」にしたのは、インド人
話は少しそれるけど、もしインド人を「家畜」として扱っていた人間がいたとしらたら、それはイギリス人ではなくインド人だ。
インドのカースト制度があることは、学校で習ったと思う。
ガンディーが活躍していた時代には、このカーストにさえ入ることができない「不可蝕民」という人々がいた。これに対して、「バラモン」・「クシャトリア」などの4つのカースト(ヴァルナ)に入っている
インド人は、「カースト・ヒンドゥー」と呼ばれていた。
不可蝕民というのは、ヒンズー社会の最下層級であり、太古の昔からカーストヒンズー(不可蝕民以外のヒンズー教徒)によって、『触れるべからざるもの』として忌避(きひ)されてきた
(アンベードカルの生涯 光文社新書)
差別の対象となった彼らの生活は、とても厳しく悲惨なものだった。
住居も、町や村外れの、不潔な、生活用水もない場所に定められ、木の葉や泥以外の家に住むことができず、その暮らしは家畜以下であった(同書)
1856年、インドの公立学校の校長が、不可蝕民の少年の入学を拒否すると、イギリスのボンベイ政府は、次のような声明を出した。
カースト、人種を理由にいかなる階級の人間に対しても教育の機会を拒否する公立学校には、政府の援助をあたえない
総ての公立学校はその全臣民(その頃、インド人は英国王の臣下として扱われた)に対し差別することなく開放すべきである(同書)
この指令を無視したのが、カーストヒンズーのインド人だった。
現在の価値観から見れば、「アウトカーストの人たちも、同じく大英帝国の臣民である」と、差別をやめるように言ったイギリス人の方が文明的だ。
ただ、よく分からなくなることもある。
この入学問題が起きた次の年に、インドで反イギリスの大反乱が起きた。このとき、イギリス人は、反乱者のインド人を大砲に詰めて打ちはなすという、恐ろしく野蛮なことをしている。
でもまったく矛盾したものではなく、植民地支配とはそういう二面性をもったものだろう。




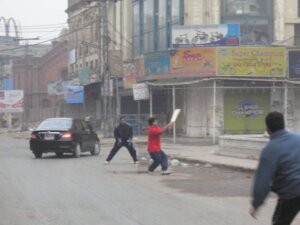



コメント