はじめの一言
「古くからの質素で健全な、自然で節度ある誠実な生活様式を捨て去る危険である。質素さを保つかぎりは、日本は強いだろう。しかし、贅沢な思考を取り入れたら、弱くなっていくと考える(小泉八雲=ラフカディオハーン 明治)」
「日本賛辞の至言33撰 ごま書房」

今回の内容
・駕籠(かご)→人力車→鉄道
・世界のリキシャ
・鉄道の登場
・列車に「土下座」する庶民
・駕籠(かご)→人力車→列車(蒸気機関車)
日本で鉄道が開通したのは、明治時代。
まえに、アメリカ人のシドモアが「魔術的指揮棒の一振りで完成させた」と表現した明治日本の変わりぶりを書いた。
こんなもの。
日本の陸海軍の創設、警察機構、行政組織は諸外国の最高例を範とし、また教育機関は完璧で、米国、英国、ドイツも制度から得た賞賛すべき最高結合体となりました。
さらには郵便制度、灯台、電信、鉄道、病院も西洋と同じ方式を採用しています。
すべてこれらは、緩慢な成長、遅鈍な発達、悠長な必要性の所産ではなく、ほとんど自発的に日本帝国の魔術的指揮棒の一振りで完成させたのです
「シドモア日本紀行 (講談社学術文庫)」
「さらには郵便制度、灯台、電信、鉄道、病院も西洋と同じ方式を採用しています」
と、サラリと書いてある。
けれど、そのどれ1つをとっても日本でそれをつくり上がることは、とてもむずかしかったはず。
今回の記事では、この中の「鉄道」をとりあげたい。

ミャンマーの列車の中の様子
シドモアが日本に来たのは、ちょうど日本の交通手段が変化しているときだった。
江戸時代の駕籠(かご)が明治になってから、和泉要助らが発明して1870年に官許された人力車へと変わっていった。
シドモアはこの人力車で日本を旅している。
しかし、1885年ごろには今度は人力車が消えていったらしい。
駕籠が人力車に負けたように、人力車は蒸気機関車を前にして消えてゆきます
「シドモア日本紀行 (講談社学術文庫)」
・世界のリキシャ
今の日本では「観光用」として人力車があるけど、タクシーのような交通機関としての人力車はもうない。
日本から姿を消した人力車は、今でもマレーシアやインド、パキスタンに行けば見ることができる。

マレーシアのリキシャ
人力車は「リキシャー」という言葉とともに輸入されて、現地の大切な移動手段となっている。
パキスタン人はウルドゥー語の「リキシャー」が、日本語の「人力車」から来ていると知って驚いていた。
今の日本人からしたら、日本語の「力車」が「リキシャー」というウルドゥー語になっていることに驚くかもしれないかもね。

インドのリキシャー
・鉄道の登場
人力車に「とどめ」をさしたのが蒸気機関車の登場だ。
1854年、日本に開国を迫ったアメリカ人のペリーが、日本人(江戸幕府の役人)に初めて蒸気機関車の模型を見せたという。
アメリカは幕府に、「ぜひ、自分たちに江戸と横浜を結ぶ鉄道を敷かせてもらいたい」と申し出ると、役人はチョウ倶楽部のように「どうぞ、どうぞ」と言ってしまう。
しかし、これが「とんでもないことだった!」と気づく。
アメリカが善意で日本に鉄道を敷(し)くことはない。
むしろ、一番高くつくのが「タダ」ということもある。
外国人に鉄道の経営をまかせると、「植民地」になってしまう可能性があるのだ。
鉄道が外国経営になると、やがてその駅や沿線まで治外法権の地、つまり日本にして日本にあらざる地、さらにいえば植民地になってしまうおそれが濃厚です。
(「明治」という国家 司馬遼太郎)
そのことに日本が気づいて、明治になってから政府がアメリカと交渉して「鉄道敷設の話はなしで!」ということにできた。
国の発展には鉄道はかかせない。
でも、明治始めの日本人には、独力で鉄道を開通する技術がなかった。
そこで、イギリス人の指導を受けることになる。
なぜ、開国をせまったアメリカが日本から消えたのか?
アメリカは、このとき南北戦争をしていたから、日本の鉄道どころじゃなかっただろう。
1872年(明治5年)、日本で初めて新橋駅ー横浜駅間で鉄道が開通した。
鉄道開通
鉄道敷設計画は、イギリス人モレルの指導下、大隈・伊藤らが進め、英国より100万ポンド(488万円)を借り、その一部で新橋駅と横浜駅間に敷設。狭軌鉄道。1872年に完成し、当時、陸蒸気といって人気を呼んだ。
「日本史用語集 (山川出版)」
この鉄道開通の指導者であったイギリス人のモレノは「日本の鉄道の恩人」といわれていて、JR桜木町駅(横浜)の近くにはモレルの碑が設置されている。
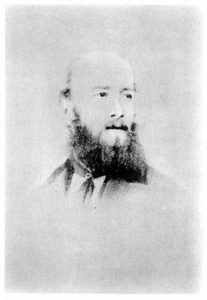
モレル(ウィキペディアから)
・列車に「土下座」する庶民
さっきのシドモアのこの記述はなんかカッコいい。
「日本帝国の魔術的指揮棒の一振りで完成させたのです」
でもこの少し前まで、日本は江戸時代だった。
庶民には、駕籠(かご)→人力車→列車といった、この急速な社会の変化についていけていない。
とくに明治時代の列車(蒸気機関車)の登場は、そのときの日本人には衝撃的だった。
大きな音を立てて走る蒸気機関車におどろいた日本人は、「土下座」をしてしまったという。
次に出てくる「陸蒸気(おかじょうき)」は、蒸気機関車のこと。
煙を吐きながら轟音を立てて走る『陸蒸気』はこの世のものとは思われなかったのだろう。蒸気機関車の轟音や振動が近付いてくると、人々はその姿を見るどころか、ひれ伏してこれを迎えたという
「定刻発車 (三戸祐子)」

次に、この当時の列車の所要時間と乗車代について。
明治5年ごろ、東京から横浜までは53分かかっている。
東京(汐留駅)から横浜(高島駅)まで二十八・八キロ、所要時間五十三分
(うたでつづる 明治の時代世相 図書館刊行会)
気になるチケットのお値段。
このろの乗車チケットには、「上等」「中等」「下等」の3種類があって、「下等」チケットだと50銭になる。
これを現在の値段で、ざっくりと換算してみる。
この本の別のページを見ると、米が1.5キロ(1升)で3銭5厘とあるから、50銭だと、大体その14.3倍。
これを単純に、現在の米1升の値段から計算する。
「ひとめぼれ」が1.5kgで約900円だから、その14.3倍となると、
東京~横浜間の「下等」の乗車代が12870円になる。
ちなみに、「上等」が38610円で、「中等」は25740円ナリ。
このときの日本で鉄道を利用できた人間なんて、どれだけいたのだろう?
本当に限られた人だけのような気はする。
けど、そのころの日本で流行した歌を見ると、案外多くの人が乗っていたのかもしれない。
馬車や人力車じゃ おそくてならぬ 早くのりたや陸蒸気
(うたでつづる 明治の時代世相 図書館刊行会)
良かったらこちらもどうぞ。









コメント