今回の内容
・イギリスでみかんが「Satsuma(さつま)」と呼ばれるワケ
・黒豚について
・黒豚の歴史
・イギリスでみかんが「Satsuma(さつま)」と呼ばれるワケ
まずは、前回までのおさらいをサラリとさせてほしい。
「イギリスではミカンのことを『Satsuma(さつま)』って呼んでいるんだぜ」
イギリス人の友人がそんなことを言う。
「さつま」は昔の鹿児島(薩摩藩)のこと。
なんでイギリスでは、ミカンを「サツマ(薩摩)と呼ぶのか?
不思議に思って調べてみると、ロンドンで暮らしている日本人のこんなブログを見つけた。
幕末期に薩英同盟が結ばれた折に友好の証として薩摩藩から英国に苗が贈られた事に由来するんだそうです。
現在のイギリスで、ミカンを「Satsuma(さつま)」と呼ばれている背景には、幕末の薩摩藩とイギリスの、戦争から始まる友好関係があったという説がある。
1863年に薩英戦争がぼっ発し、「両者痛み分け」のような結果に終わり、賠償交渉が始められた。それが進むうちに、薩摩がイギリスに「baskets of fruit(果物のバスケット)」が贈られたという記録が残っているという。
鹿児島経済大の助教授だった宮沢真一さんがその記録を調べ、バスケットにはミカンが入っていたのではないかと推測している。
朝日新聞のコラム『サツマ編2 仲直りの品? 船の食料?』(2018年03月30日)そんなことが書いてある。
これがイギリスにおける「Satsuma」の始まりかもしれない。
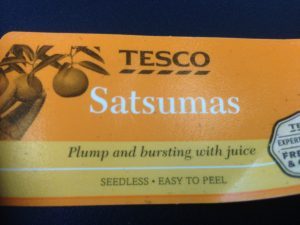
ロンドンのスーパーでは「Satsuma」という名称でミカンが売られている。
・黒豚について
現在のイギリスで「サツマ」といえばミカンのことをさす。
では今の日本で「サツマ」といえば何のことか?
これは黒豚を意味する。
ということで、これからみんな大好き黒豚について書いていきたい。
先ほどのブログにはこんな一文がある。
反対に英国から薩摩藩に贈られたのがバークシャー種の豚で、
これと在来種を掛け合わせたりして改良されたのが現在の黒豚なんだって~。
薩摩藩からイギリスにミカンの苗が贈られて、そのお礼にイギリスが薩摩藩にバークシャー種の豚が贈られた。
そしてそのことによって、鹿児島の黒豚が誕生した。
話としては面白い。
けど、どこまで事実かはちょっと分からない。

・黒豚の歴史
「薩摩と豚」の関係は昔から深かった。
戦国時代、薩摩の国では豚肉を「歩く野菜」と呼んでよく食べられていたという。
なんで歩く「野菜」なのか分からない。
どう見ても「肉のかたまり」なのだが。
ただ薩摩藩が戦国時代の日本のなかで、異色(異食?)の藩だったことは間違いない。
大名の島津氏は織田信長よりも先に鉄砲の実用化をおこなったし、肉食がタブー視されていたこの時代に、薩摩藩は生きた豚を食用として戦場に運んでいたのだ。
この薩摩の豚にイギリスのバークシャー種の豚をあわせて、品種改良した豚が「黒豚」になる。
肉質が優れているとされるバークシャー種と交配することで、黒豚のよいところを引き出しながらそのおいしさに一層 の磨きをかけ、豚肉の芸術品を完成させました。
これが1895年ごろという。
日清戦争の講和条約である、下関条約が結ばれた年だ。
だからこのころは、もう薩摩藩ではなくて鹿児島県になっていたはず。
それからも鹿児島では、黒豚の品種改良を続けた。
そして、ついに「サツマ」という画期的な黒豚を生み出すことに成功する。
かごしま黒豚の品種改良では、昭和57年に系統豚「サツマ」を完成。個体のばらつきが小さく、斉一性も繁殖能力も産 肉能力も高い黒豚が生まれました。また、平成3年には、イギリスバークシャーを基礎とした系統豚「ニューサツマ」が完成しました。
鹿児島では、ここにある「ニューサツマ」の他にも「サツマ2001」という品種の黒豚も誕生させている。
ということで、現在のイギリスで「Satsuma(サツマ)」といえばミカンのことをいう。
そして日本で「サツマ」といえば黒豚のことをいう。
今夜はトンカツだな。
おまけ
アメリカでもみかんが「サツマ」と呼ばれている。
1878年、アメリカの駐日公使だったヴァルケンバーグ将軍の妻が薩摩から、みかんをアメリカに持ち込み、ヴァルケンバーグ将軍はそれを「薩摩」と命名した。
ソース:Citrus unshiu
今回の復習
・薩摩藩では戦国時代に豚はなんと呼ばれていたか?
・戦国時代、島津氏は織田信長よりも先に何の実用化をおこなった?
・日清戦争の講和条約はなに?
答え
・歩く野菜
・鉄砲の実用化
・下関条約
こちらの記事もいかがですか?
英仏で尊敬される人物。チャーチルとドゴールが英雄である理由とは









コメント