20年ぐらい前にタイを旅行していて、衝撃的だったことにタイ人の”ゆるさ”がある。
たとえばこの観光バスの運転手、博物館(たぶん)で乗客を降ろした後、自分のバスとそこらの柱でハンモックを吊って、裸足になって携帯をいじり始めやがりました。

いまでもコレが許されるかは知らない。
ただ日本に比べればタイでは全体的に、自分のやりたいことを好きにやれるリラックス&自由な空気はある。
そんなタイでも歴史をみてみると、日本との共通点がけっこうあったりする。
・同じアジア人で仏教の影響が強い。
・日本に皇室があればタイには王室があって、むかしから友好交流が続けられている。
・19~20世紀の帝国主義の時代、日本もタイも欧米列強のプレッシャーに負けず、近代化を実現して独立を守り抜いた。
このほかにも、日タイでは国名を変更した理由も同じだ。”同じ”というのは言い過ぎかもだけど、国名を変えようとした動機はかなり似ている。
まず、それまで「倭(国)」だったこの国が、「日本」という名称に変更されたのは7世紀後半のこと。
日本を「倭」と呼んでいたのは中国人で、この漢字には「背の曲がった小人」というネガティブな意味があったのだ。
「倭」は蔑称だったから日本人はこれを嫌って、飛鳥時代に「日本」という新しい国名を考案して現在まで続いている。
詳しいことはこの記事を。
タイの場合、それまで「シャム」だった国名が1939年6月24日に「タイ」へと変更された。
「Siam(シャム)」のタイ語の発音は「サイアム」で、首都を走るバンコク・スカイトレイン(BTS)にはこの旧国名に由来する「サイアム駅」がある。
タイ政府が国名を「シャム」から「タイ(Thailand)」へ変えた理由について、外務省ホームページにはこう書いてある。
「サヤム」「シャム」は外国人の呼称で属国の意味もあるため適当でなく,「タイ」人の「タイ」国であるという観念を強調するための国名改称であると報じられました。
「倭」と同じように、「シャム」も外国人の呼び方でネガティブな意味が込められていた。
さらにいうと、7世紀ごろは中国も日本を属国のように考えていたはず。
そんなことからタイ政府はこの”蔑称”から、「自由」をあらわす「タイ」へ変更したのだ。
詳しいことは東京都立図書館の「タイ王国」で確認のこと。
まえにタイ人の日本語ガイドから、いまでも試験が終わって解放されると「タイ(自由)になった~」なんて言うと聞いた。
タイ政府はその後、1945年に国名をまたシャムに戻したものの、1949年のきょう5月11日にまた「タイ」へ戻して現在まで続いている。
ということで、7世紀と20世紀という時代の違いはあっても、外国人から「上から目線」で侮辱的に呼ばれていた国名を、自分たちで変更したという点で日本とタイは同じだ。
中国文化の日本文化への影響②日本風にアレンジした5つの具体例。








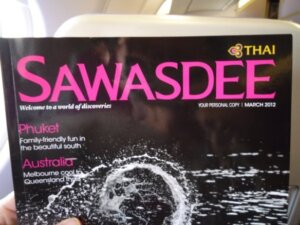
コメント