日本にある「実は“100年超え”のロングセラー商品」とはなにか?
gooがそんな調査をして、「gooランキング」で発表している。
日本人の身近にあるもので、「でもこれ、じつは100年以上の歴史があるんですよ」と聞いて驚いたものがランクされる。
今回の記事では、歴史の勉強をしながらランキングを紹介していきたいと思う。
調査の結果、日本人が一番驚いたロングセラー商品は「三ツ矢サイダー」だった。
もはや日本の国民飲料ともいえる「三ツ矢サイダー」が第1位になっている。
下の「gooランキング」のサイトに結果がある。
日本で初めてサイダーがつくられたのが1881年。
そして初めて販売されたのは1884年。
アサヒ飲料のホームページにサイダーの歴史が書いてある。
約130年の歴史をもつ、三ツ矢サイダー。明治14年(1881年)、ウィリアム・ガランというイギリス化学者が、平野鉱泉を飲み物として「理想的な鉱泉」として認めたことで、炭酸水の製造をはじめ、明治17(1884)年に「平野水」として発売されたのがはじまりです。
「アカデミー 三ツ矢豆知識」
サイダーが登場した1884年のころ日本は文明化のまっ最中で、鹿鳴館(ろくめいかん)で外国人と踊っていたころだ。
中国の古典『詩経』に由来する鹿鳴館は西洋の風俗や習慣を取り入れて、欧米と結んだ不平等条約の改正をねらったが、結局これはうまくいかず。
サイダーが生まれたころ、日本の社会は本当に変わっていった。
1885年には、伊藤博文が初代の内閣総理大臣になっている。
1887年には、東京に電灯がついた。
1890年には、今なにかと話題の教育勅語が発布されてる。

サイダーに似た飲み物に「ラムネ」がある。
ラムネという言葉がどうやって出来たか、ご存知だろうか。
この元ネタは英語の「lemonade(レモネード)」だ。
ラムネ
清涼飲料の一種。レモネード lemonadeが転訛した呼称で,日本独特のもの。成分はサイダーとほとんど同じ炭酸飲料だが,特徴ある瓶によって親しまれている。
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典
このラムネが製造されたのは、サイダーよりも早い。
1865年の長崎で、日本で初となるレモネードがつくられた。
この2年後の1867年に大政奉還によって江戸幕府は終わった。
サイダーの炭酸水から、文明開化の音が聞こえ始めていた。
このラムネが日本で初めて販売されたのは、1872年5月4日。
今では、この日がラムネの日になっている。
「全国清涼飲料協同連合会」のホームページにそのことがかいてある。
ラムネの製造販売をはじめたのは、東京の千葉勝五郎という人物で、1872年(明治5年)の5月4日とも言われています。
「ラムネの語源は英語のレモネードだった」と話すと、イギリス人の友人が驚いた。
前からラムネという日本語は知っていたけど、その発音から「lemonade」を思い浮かべたことは一度もなかったらしい。
「でもそう言われてみたら、味はレモネードに近いかも」てなことを言う。
そのイギリス人はよくレモネードを作って飲んでいた。
イギリスで「夏のイメージ」といえば、炭酸水にレモンを入れたレモネードがあるらしい。
日本でいうスイカみたいなもんか。
ランキングの結果は下のサイトにあるからよかったらどうぞ。
三ツ矢サイダーも!実は“100年超え”のロングセラー商品ランキング
こちらの記事もどうぞ。
日本人の食文化:江戸は犬肉を、明治はカエル入りカレーを食べていた

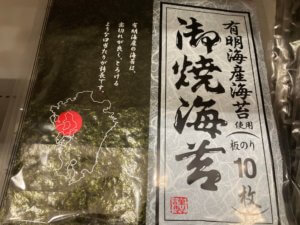







コメント