日本とイギリスの歴史には、4月14日にこんな出来事があった。
平安時代の969年、醍醐天皇の皇子で左大臣だった源高明(みなもとのたかあきら)が密告によって九州の大宰府に左遷された(安和の変)。藤原氏はこれで政敵を追放することに成功し、朝廷で実権を握るようになった。 一方、イギリスでは1471年にランカスター家とヨーク家の戦い(薔薇戦争)で重要なバーネットの戦いが行われた。
安和の変とバーネットの戦いは、どちらも国内の貴族による権力争いだが、その内容はかなり違う。もし、源氏と藤原氏が軍隊を持ち、武力で決着をつけようとしていたら、薔薇戦争のような内戦状態になっていただろう。
ヨーロッパの歴史では、貴族が軍を率いて進軍し、戦場で戦うことはよくあったが、日本の歴史ではそれが本当に少ない。奈良時代の後期から平安時代初期にかけて活躍した坂上田村麻呂は、征夷大将軍としてみずから軍を率い、東北へ遠征してアルテイらと戦った。しかし、こうした例は“劇レア”で、現代の日本人は平安貴族に「武将」のイメージを持っていないと思う。
1156年、皇位継承をめぐって保元の乱が起き、後白河天皇サイドと崇徳上皇サイドに朝廷が二分された。このときも貴族たちは、お互いが直接戦うことはなく、戦闘は武士にまかせて問題を解決しようとした。その結果、後白河天皇側が勝利したが、武士が活躍することでその台頭を許し、平清盛による日本初の武家政権「平氏政権」が生まれた。
天台宗の僧・慈円が『愚管抄』に「ムサ(武者)の世になりにけるなり」と書いたように、保元の乱を前後して日本のパワーバランスは大きく変わり、政治の実権は貴族ではなく、武士が握るようになった。その後、本格的な武家政権である鎌倉幕府が誕生し、「武者の世」は決定的となり、その後約700年後、朝廷は政治の舞台から追い出されることになる。
なぜ平安時代の貴族が軍隊を持って戦わなかったのか?
AIに質問したり自力で調べたりすると、次のような理由が見つかった。
・平安時代、軍事の指揮権は基本的に中央政府(朝廷)が握っていて、貴族一人一人はおもに政治や文化活動に専念し、軍事活動にはほとんど関与しなかった。
・平安時代は大規模な戦争が少なく、わりと平和な時代だったため、貴族たちは軍事力を持つ必要がなく、いざとなったら、武士にさせればいいと考えていた。
・貴族たちの価値観では、武力よりも学問や文化、礼儀作法が重要視され、戦闘から遠ざかっていて、軍隊を持つことにあまり関心がなかった。
これらの要因から、貴族たちは武力(軍隊)を持たず、結果的にそれを担った武士に政治の権利を奪われ、乗っ取られてしまった。
さらに、平安時代の貴族たちは、死や血を「穢れ」として忌み嫌ったり、恨みを残して死んだ人間が怨霊となって祟ると信じていたため、戦闘を避けていた可能性がある。
930年、内裏の清涼殿に雷が落ち、複数の貴族が焼かれて苦しみながら死んだ。この時、神聖な清涼殿に死の穢れが触れたことが大騒ぎとなった(清涼殿落雷事件)。また、平安時代の天皇や貴族は、無念の死をとげた人間が怨霊となって復讐すると考え、恐れていた。
死や血を“穢れ”として忌み嫌ったり、御霊信仰を信じたりしていたため、平安時代の貴族はみずから軍を率いて戦うことを嫌がったのだろう。
歴史の「タラレバ」は自由に想像できる。
貴族たちが戦ったイギリスの薔薇戦争のように、保元の乱でも、平安貴族が軍を率いて戦って争いを解決していたら、きっと武士つけ入るスキを与えていなかった。もし日本の貴族が特権を享受することと引き換えに、戦闘というリスクを引き受けていたら、ヨーロッパの歴史のように武家政権が誕生することはなく、「武者の世」にもなっていなかったと愚行する。

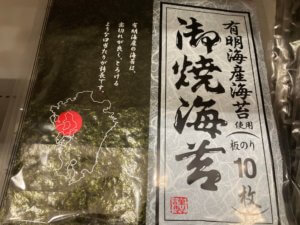







コメント