「天は二物を与える」ということはマレにあって、現在、メジャーリーグで大谷選手が「二刀流」を実現している。大谷選手のような銀河系レベルのスターは別として、一般的には、本業で優れた結果を出し、趣味でも素人離れした知識や技術を持つ「二刀流」が多い。
将軍や皇帝なら、民衆を幸せにする素晴らしい政治を行えば、それだけで「名君」と称賛され、さらに文化人としての才能があれば、尊敬はさらに高まる。
これから紹介する2人は、残念ながらその逆だ。
5月21日は、1449年に足利義政が室町幕府の第8代将軍に就任した日。
義政は後に「銀閣寺」と呼ばれる東山殿をつくり、文化や芸術を愛した人物で、庭師や絵師、能楽者などを召し抱え、わび・さびを重視する「東山文化」を築いた。彼自身もたくさんの和歌を詠み、現在では1500首ほどが伝わっている。
東山文化に能、茶道、華道、庭園、建築、連歌などが発展し、現代の日本文化の基礎となったものも多い。
一方で、この時代には応仁の乱(1467年)が起こり、戦場となった京都では多くの建物が焼かれ、壊滅的なダメージを受けた。応仁の乱を描いた『応仁記』には、当時の惨状を目撃した人の感想が記されている。
「天下は破れば破れよ、世間は滅びば滅びよ、人はともあれ我が身さえ富貴ならば」
応仁の乱は人々の心を荒廃させただけでなく、室町幕府が権威を失うきっかけとなり、結果的に、日本を戦国時代という乱世へ導いた。そして、足利義政はそれを防げず、民衆が飢えで苦しんでいるのに豪華な新邸を建てたため、政治的には「無能」と評価されることが多い。

徽宗が描いたとされる桃鳩図(ももはとず)。現在、桃鳩図は日本にあって重要文化財に指定されている。
室町幕府の第8代将軍・足利義政が「無能将軍」なら、北宋の第8代皇帝・徽宗(きそう)は「無能皇帝」だ。
徽宗(1082~1135)は文化人としては一流の人物で、優れた書や絵画を生み出し、北宋時代の最高の芸術家の一人と称賛されている。彼には造園の才能もあり、造園に必要な珍しい花や名木、太湖石などの奇石を全国から集めさせた。徽宗は才能があるだけでなく、多くの芸術家を保護したため、「風流天子」とも呼ばれた。
しかし、皇帝としては無能だった。
各地から木や石を首都・開封に運ばせるためには、とんでもない費用と労働力が必要で、輸送の邪魔になる民家や橋を破壊したため、彼は民衆から深く恨まれた。これが、「方臘(ほうろう)の乱」の原因となる。当時の中国人も「天下は破れば破れよ、世間は滅びば滅びよ」という状態だったと思われる。
徽宗の政治で世の中が乱れ、人々が悪政に苦しんだことから、その時代が『水滸伝』のモデルとなった。徽宗の無能さがなかったら、きっと『水滸伝』は生まれなかった。
1126年、北方から金が攻めてきて、開封を陥落させると、徽宗は捕虜として連行された(靖康の変)。彼は北宋にトドメを刺したような皇帝だったため、後世の中国人からは、
「皇帝に即位すると芸術のために重税と浪費を行い、民衆を苦しめて自分の耳目鼻口(五感)の楽しみにふけった」
と厳しく批判された。
足利義政は応仁の乱を止めることができず、室町幕府の弱体化を招いたが、滅亡させることはなかった。「無能レベル」でいうなら、徽宗のほうが上かもしれないが、文化人としての資質では徽宗は義政の上位互換だった。
義政については、「ダメ将軍」と言われることが鉄板になっていたから、最近は逆張りで、彼のポジティブな面を見つけようとする動きもある。中国で、徽宗について再評価の動きがあるという話は聞いたことがない。この皇帝はちょっと救いようがない。

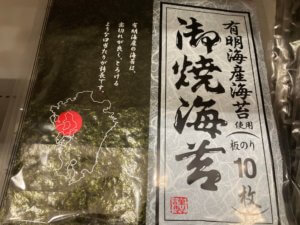







コメント