友人に、日本の企業で働いているイスラム教徒のトルコ人がいる。
彼はコーヒーが好きだから、今年3月、カフェでコーヒーでも飲みながら話をしようとメールで誘うと、その日は午後から空いているけれど、カフェで会うことはできないと断られてしまった。なので、7時にレストランで夕食を食べることになった。
そこで彼と交わした会話の様子がこちら。
ーーそっか、今はラマダンの真っ最中だったっけ。神聖なラマダン月の間、イスラム教徒は日が沈むまで断食をしないといけない。
そう。この期間中は、昼間にカフェでコーヒーを飲むことはできないんだ。すまない。
ーーいや大丈夫。「空いてるけど会えない」って言われたら、「なぜ嫌われた?」ってあせるけど、ラマダンと聞いてむしろ安心した。イスラム教徒にとって、ラマダンの断食は絶対だからね。
でも、例外のないルールはない。病人や旅行者、妊婦などはラマダン中の断食を免除されている。イスラム教は柔軟性があって、人に配慮された宗教なんだよ。
ーーボクも2012年のロンドン五輪でそう思った。
大会期間とラマダン月が重なって、イスラム教徒の選手が断食をするべきか議論になったとき、エジプトの宗教指導者は「選手は“旅行者”になるから、断食する必要はない」という見解を示した。ボクからすると、斬新でアクロバティックな発想だったね。
まぁ、そういう解釈もできるんだろうね。
私からすると、パチンコがギャンブルに相当しないという日本の論理にビックリした。
ーーあ〜、三店方式か。
客のパチンコ玉を店が「景品」に交換して、その景品を交換所に持っていくと現金に換金してくれる。だから、法的には完全にOKで、これはギャンブルではない。
…という理論に納得した外国人なんて見たことないw
日本人は法律やルールを厳格に守るから、社会に規律がある。そこがトルコと違って感心するけど、意外と「ズルい」ところもある。
ーーお褒めいただいて光栄だ。

ーーイスラム教では、賭け事は不当な利益を生んで、憎しみや負の感情をあおるから禁止されているんだっけ。ポケモンカードを交換することもギャンブルの一種、「悪魔の行為」と考えられて、カタールでは禁止されたと知って世界が違いすぎると思った。
パチンコなんて絶対ダメでしょ。
ピカチュウ(ポケモン)の進化は、「反イスラム教」だから禁止です
イスラム教では、ギャンブルは厳禁されているからね。でも、何をギャンブルとするかの解釈は国によって違う。
同じイスラム教徒でも、考え方はいろいろある。一般的にはアルコールを飲むことは禁止されているけど、トルコのイスラム教徒は平気で飲んでいるよ。
ーーそう、それ。
「イスラム教徒は酒と豚肉を口にすることができない」って学校で習ったから、トルコに行ったとき、「ラク」ってアルコール度数の高い蒸留酒が人気だと知って、「イスラム教って意外と楽なのか?」とびっくりした。
クルアーン(コーラン)には、実は「酒を飲むな」とは書かれていないんだ。酔っ払って、神やイスラム教徒の義務を忘れることが禁止されていて、アルコールを飲むこと自体はいいんだよ。
*これは彼の個人的な意見で、普通イスラム教徒は酒を飲まない。
ーー江戸時代、不正を一切許さない超クリーンな社会よりも、ズルさが認められる社会のほうが住みやすかったと庶民が嘆いたこともあった。
いつの時代のどの国にも、法やルールを「柔軟」に解釈するゆとりが必要なんだろうな。
ギャンブルは儲かるから、イスラム圏でもそのうち、「三店方式」を採用する国が現れるかも。
いや、それはない。
*江戸時代、白河藩主の松平定信が寛政の改革を行ったころ、こんな川柳が流行った。
「白河の 清きに魚も すみかねて もとの濁(にご)りの 田沼恋しき」
田沼意次の時代に「賄賂政治」が横行していて、次の松平定信はそんな腐敗を嫌い、庶民にも厳しくルールを守ることを要求した。そのため、清くて正しい今の世の中よりも、濁っていた田沼の時代の方が居心地がよかったと庶民が懐かしんだ。
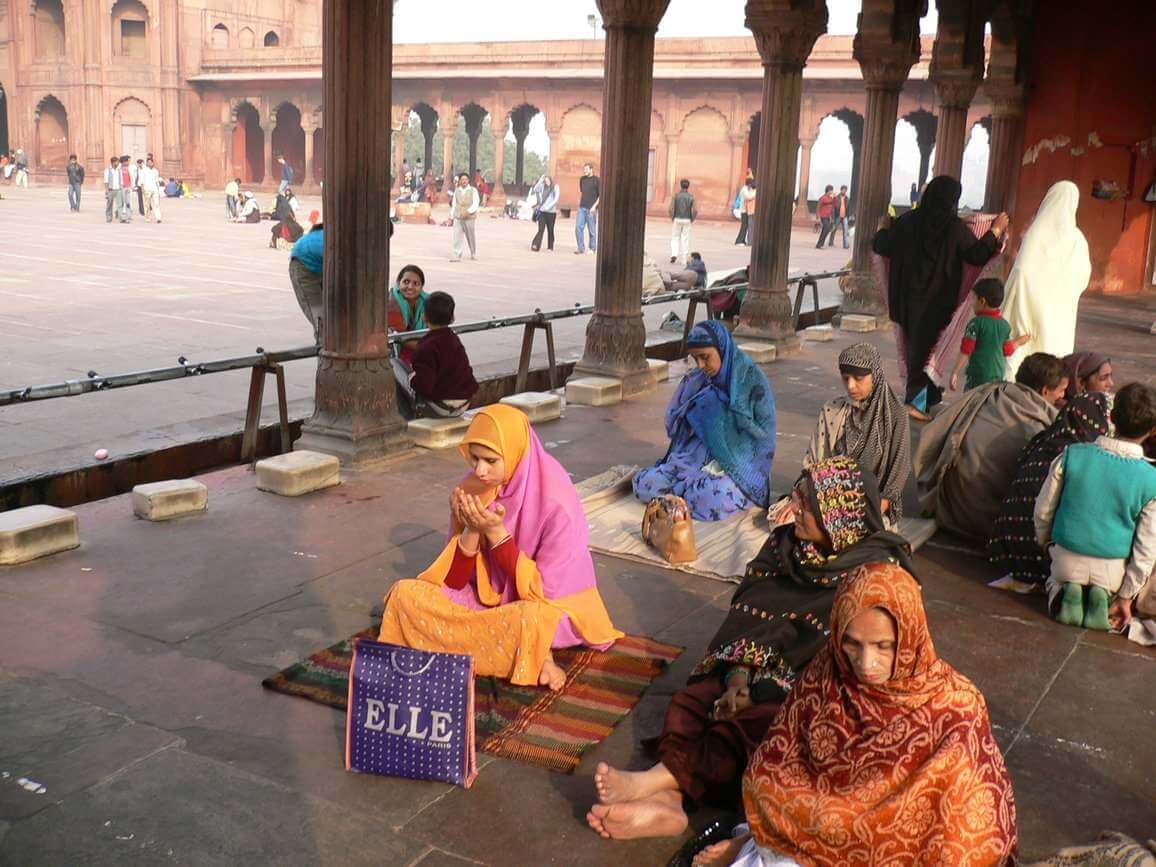
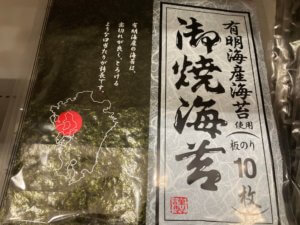







コメント
コメント一覧 (2件)
> もとの濁(にご)りの 田沼恋しき
その田沼時代の江戸で隆盛を極めた「吉原遊郭」と、浮世絵や貸本など娯楽のプロデューサーとして吉原遊郭を中心に活躍した「蔦屋重三郎」の生涯を、今のNHK大河ドラマ「べらぼう」では生き生きと描いています。しょせんは女郎の世界ですから、女達にとっては辛いことの多い「生業(なりわい)」です。それでも、蔦重その他多くの人々が紡ぎだす「庶民文化」を精一杯楽しみながら、一生懸命に生きている。ある程度の自治権を有し、互いに助け合ったり、競争したり、喧嘩をしたりもする。
おそらく、他の国では、売春婦の世界にこのような文化や暮らしはほぼ存在せず、搾取する側とされる側での「性奴隷」の関係だけがあったのでしょう。なぜなら江戸と違って、外国には、そのような庶民の風俗についての記録がほとんど存在しないからです。(あるいは抹消されてしまったか?)
江戸庶民の文化について興味がある外国人には、従来にはない、たいへんお勧めできるドラマです。
幕末・明治時代に日本へ来た欧米人が、日本では、遊郭にいる「売春婦」が社会的に蔑視されていないことに驚きました。