現在ではあまり使われていないけれど、英語に「Camel’s nose」(ラクダの鼻)」という言葉がある。
あるとき、砂漠でラクダがテントにいた人に、鼻だけ入れてほしいとお願いをした。中の人は「鼻だけならいいか」と許したが、ラクダは頭、そして体まですっぽりテントに入ってきて、ついにはテントを乗っ取ってしまった。
そんなアラビアの話がヨーロッパに伝わり、「小さな行為を認めると、あとで取り返しのつかない事態を招く」という意味で「ラクダの鼻」という言葉が英語でも使われるようになった。
日本語にも「庇(ひさし)を貸して母屋を取られる」という言葉がある。小さな譲歩をしたら、すべてを失ったという事例はどの国にもあるのだろう。

以仁王
6月20日は、1180年に以仁王(もちひとおう)が亡くなった日。彼の命日だ。R.I.P(安らかに眠れ)。
以仁王は後白河天皇の子で、皇族の一人だった。
彼は「令旨(りょうじ)をもって命じる。平家を討て」と全国の源氏に呼びかけたことで知られている。
※ちなみに、天皇が出す命令は「宣旨(せんじ)」、皇太子が出す命令は「令旨」と呼ばれる。以仁王は皇太子(第一継承者)ではなかったのだが、命令の効力(正統性)を高めるため、あえて令旨という形にした。
1156年、朝廷内で権力をめぐる争い「保元の乱」が起こると、武士の平清盛は後白河天皇に味方して戦い、勝利をもたらした。しかし、後白河は平清盛の力を借りたことで、清盛が政治の世界に進出するきっかけを作ってしまう。
これが日本初の武家政権(平氏政権)の誕生につながった。
しかし、清盛の台頭が気に食わない貴族たちも多かった。
1177年、後白河法皇の側近たちは平家を倒して政治の力を取り戻そうと計画していたが、それが清盛にバレてしまい、関係者は処刑されたり遠くに流されたりした。
後白河は側近を失い、政治的権力も大きく低下する。
怒った後白河は、なんとか平家を朝廷から追い出そうと動いたが、1179年、それを察知した清盛が先に動き、武力によるクーデターを起こした。これが「治承三年の政変」だ。
清盛は後白河を捕らえて幽閉し、最大の敵を排除した。彼は高倉上皇や安徳天皇を思い通りに動かすことができ、日本の最高実力者となった。
後白河にとっては、朝廷を乗っ取られたようなもの。思い返せば、あの「保元の乱」で清盛の力を借りたことが、まさに「ラクダの鼻」だった。
清盛の軍事クーデター(治承三年の政変)で、後白河の第三皇子・以仁王も巻き込まれ、自分の土地を没収され、経済的な基盤を失った。
これが原因となり、以仁王は「令旨(りょうじ)をもって命じる、平家を討て」と各地の源氏に令旨を出し、自らも兵をあげた。
これが「治承・寿永の乱」、つまり有名な源平合戦の始まりになる。
平家側(この時点で清盛はすでに死去)は激怒し、以仁王を「臣籍降下(しんせきこうか)」、つまり皇族から外して一般人扱いにした上で攻撃し、現在の京都・宇治市で討ち取った。
※皇族のままでは殺すことができなかったため、身分を落としたのだと思われる。
しかし、伊豆にいた源頼朝がこの「以仁王の令旨」を受け取って立ち上がり、弟の天才軍師・源義経もこれに加わった。そして1185年、ついに壇ノ浦の戦いで平家を滅ぼした。
その後、頼朝は鎌倉幕府をつくり、日本は約700年間、武士が政治を動かすこととなる。
朝廷は平家を倒すことには成功したが、その代わりに政治の力を武士に奪われてしまった。このすべての始まり──つまり「ラクダの鼻」を探すなら、やっぱり「保元の乱」だろう。

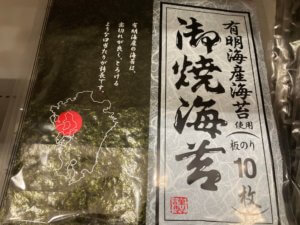







コメント